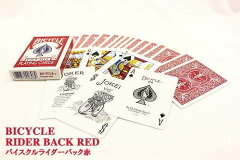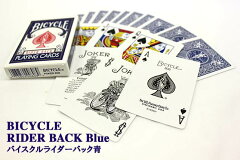Advertisement
はいどうもsobogaです。
今回は、日本人に最も馴染みのありそうなシャッフル「ヒンズーシャッフル」の解説です。
Trick Libraryでは、「カードの基礎」の「シャッフル」のカテゴリに分類しています。難易度は[初級]です。
技術的には非常に簡単なシャッフルで、分類的にはオーバーハンドシャッフルのバリエーションに当たるものですが、このシャッフルをやり慣れていない、そして見慣れていない欧米の人にとっては奇妙な混ぜ方に映るようです。
日本においての、技法名のカタカナ表記では「ヒンズー」だったり「ヒンドゥー」だったり表記ゆれが目立ちます。英語表記だと「Hindu」なので、本来は「ヒンドゥー」がより発音に近く正しいように思われますが、Trick Libraryでは「ヒンズー」で統一しています。
それでは早速、解説していきましょう。
Advertisement
ヒンズーシャッフルのやり方
デックの持ち方

通常のディーリングポジションから人差し指でデックを押し上げて、エレベイティドディーリングポジションで持ちます。「エレベイティドディーリングポジション」、あまり聞き慣れない方もいそうですが、手のひらから離した、指先で持つディーリングポジションのことです。以前の「ディーリングポジション」の解説の中で説明しているので、詳細を知りたい方はそちらを参照してください。
そしてこの次が、日本人のよくやるシャッフルと違う持ち方になる箇所です。

左手小指をどけて、右手の甲が上を向く形で、イン側エンド付近の両サイドを、親指と中指・薬指の三本の指先でつかみます。仮に、この時点で左手を離したとしても、右手だけでデックが保持されるようにしっかりとつかんでください。

人差し指と小指は適当です。こんな、はしゃいだ形でなければなんでもいいです。はしゃぎたかったらはしゃいでもいいですけど。

右手がデックをつかんだら、左手はデックのトップから5〜10枚ずつのパケットを左手に取っていく準備です。アウト側エンド付近の両サイドを、左手の親指と中指・薬指でつかみます。このときの三本の指は指先よりも第一関節付近を使うと、取る枚数のコントロールがしやすくなります。
シャッフルのやり方

左手の三本の指でトップ5〜10枚をつかんだら、右手を手前に引いて、つかんだパケットだけが左手に残るようにします。

右手の残りパケットが完全に左手から外れたら、左手のパケットをつかんでいる指を離して、ちょうどディーリングポジションに収まる箇所に落とします。このときの左手の前後の角度は、少し観客側に傾くかたちで、パケットが滑り落ちていかないように人差し指がガードしています。
これで1回分のシャッフル完了です。
同じことを右手のパケットがなくなるまで繰り返します。一度のヒンズーシャッフルが7〜10回のシャッフルで終わるように、左手でつかむパケットの枚数をコントロールしてください。
ここで、突き詰めて考えたときに1つ疑問が湧くかもしれません。
左手を動かすのか?右手を動かすのか?それとも両手を動かすのか?
「ロベルト・ジョビーのカード・カレッジ第1巻」には右手は固定して、左手を動かすと書いてあります。
「カードマジック事典」や「カードマジック入門事典」には、どちらを動かすかは明記されていませんが、「右手で残りパケットを引き出す」という感じの書き方をしているので、おそらくですが右手を動かす想定なのかなと推測できます。
それから、僕が昔カードマジックを習ったときの先生からは「両手を動かす」と習いました。


どれがいいんでしょうね?まあ、はっきり言ってどれでも好きなようにやればいいと思いますが、僕は、昔習ったまま「両手を動かす」派です。理由は、それが最も効率的だからですね。右にしろ左にしろ、どちらかを固定する場合は、動かす手は1デック分動かなければならないわけですよね。ところが、両手を動かせば、右手も左手も半デック分で済むんですよね。そういうことです。どうでもいいこだわりだなと思った方は、この話は完全スルーでいいと思います。
まとめ
以上、ヒンズーシャッフルの解説でした。
ヒンズーシャッフルの性質
先に、ヒンズーシャッフルはオーバーハンドシャッフルのバリエーションだっていう話をしましたが、技法の性質はオーバーハンドシャッフルのそれとは異なります。
ランができない
まず、「ラン」ができないため、オーバーハンドシャッフルと同じ手法ではトップやボトムを変えずにシャッフルすることができません。

えっと、正確に言えば、やろうと思えばランはできるんですけど、こうやってやれば。でも、通常のシャッフルとランの見た目がだいぶ違ってくるので、これは得策ではなさそうですよね。
ヒンズーシャッフルで、通常のシャッフルに見えて、トップやボトムを変えないためにはシークレットムーブを行わないといけないので、それは別の解説にゆずることにします。
日本人にとって見慣れている
もしかしたらこれは結構重要なことかもしれません。
日本人の一般の観客にとって最も見慣れているのがヒンズーシャッフルで、他のどのシャッフルよりも、「混ぜた」という印象を観客の無意識に強く植え付けるのはこれなんじゃないかなと思っています。
そして、自分のよく知っている混ぜ方で、シークレットムーブが行えるとは思っていない可能性も高いですよね。
なので特にメンタルマジックを演じるときは、技術の華麗さを一切封印して、ヒンズーシャッフル一本で通すことをおすすめします。
見た目には地味ですが、ヒンズーシャッフルの使いどころもちゃんとあるんだよという話でした。
では、また。
sobogaの蛇足
「ヒンズーシャッフル」という技法名ですが、カードマジック事典の説明を引用しますね。
「ヒンズー」という名は, 欧米においてインドの奇術家たちがこのシャフルを用いたことに由来する.
高木重朗 編 カードマジック事典 21版 p.40
Web上でもこれに影響を受けてか、同じような記述がいくつか見られますが、これ本当に変な由来だなあと思っています。
出典、文献、ソースが不明なのと、「いつ」「どこで」「誰が」の記述を一切見つけられないので本当のところはわからないんですが、ソースやそれらしいストーリーを知っている人がいたらぜひ教えて下さい。
インドの奇術家がやってたシャッフル → インドのシャッフル → インドといえばヒンズー教 → だからヒンズーシャッフル
なんで?なんでそうなる?なんで「インドといえばヒンズー教」をはさんだ?
確かにインド人の90%以上はヒンズー教だけれども、もし、エジプト人が独特なシャッフルをしているのを目にしたら、エジプト人の90%はイスラム教なので「イスラムシャッフル」になるの?ならなそうだよね。ぜんぜんわからん。
どうでもいい、sobogaの蛇足でした。
あらためて、では、また。
参考文献
おすすめカード
関連記事
Advertisement