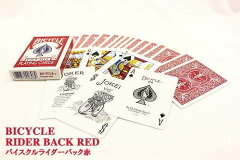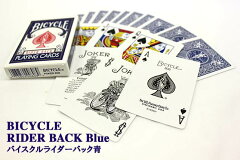Advertisement
はいどうもsobogaです。
今回は、かなり用語集的な回で「リフル」についての解説です。「リフルシャッフル」でもなく、「リフル〇〇」でもなくリフルそのものの解説です。
完全にカードマジック初学者に向けた動画(記事)になりますが、自分の生徒さんなんかを見て痛感するのが、意外とこういう基礎的な動作でつまずく人が少なくないってこと。あえてわかりやすく言うと、大抵の人はリフルが下手くそだっていうことです。学び始めは、ですよ。
「リフルシャッフル」で考えてみても、リフル自体の習熟度によって見た目の印象がぜんぜん違って見えてくるので、あらためて1本の記事にしてみました。
Trick Libraryでは、「カードの基礎」の「その他」とフラリッシュのカテゴリに分類しています。難易度は[初級]です。
それでは解説です。
Advertisement
「リフル」は「パラパラめくること」で、本を指で弾いてめくる動作をイメージすればわかりやすいですかね。ただ、本に比べてカードは小さくて、1枚1枚が厚くて硬いので難易度は少し上がるようです。
一口にリフルといっても、使う指もリフルする箇所もリフルする目的もいろいろあるので順に見ていきましょう。
エンドリフル
手前エンドをリフルする
やり方
手前エンドのリフルです。使う指は右手親指です。


特殊な持ち方をしない限りは右手だけでは成立しないやり方で、左手なりなんなりの支えがなければ「ドリブル」のように弾かれたカードは下に落ちていきます。つまりドリブルも一種のリフルだってことですね。

ディーリングポジションのままでもできますが、エレベイティドディーリングポジションで持てばさらにやりやすくなるし、見た目も良くなると感じます。
使いみち
使いみちは、主にリフルシャッフルのリフルです。

2つのパケットに分けるときもそうだし


パケットを噛み合わせるときのリフルも両手で親指でのエンドリフルです。このときは左右とも片手でリフルすることになるので、ちょっと特殊な持ち方になりますね。
観客側エンドをリフルする
やり方
観客側エンドのリフルです。中指か人差し指のどちらか、または中指と薬指の両方を使います。個人的には中指だけのほうがやりやすいですかね。

ディーリングポジションに持って、トップカードの真ん中に当てた親指が支点になります。そのときに、右サイドの3本の指は真ん中から手前側をつかむようにすると、よりやりやすくなると思います。

右手親指を手前エンドにしっかりと当てて、該当の指で観客側エンドをひっかくようにリフルします。
使いみち
使いみちはいくつか考えられます。
1つ目は、観客のカードをランダムな場所に戻してもらうときです。
観客側エンドをゆっくりとリフルしていって、観客のタイミングでストップかけてもらい、デックの別れた箇所に差し込んでもらいます。

次はフラリッシュ的な使い方ですが、リフルの風圧でテーブル上のカードやカードケースを動かすっていうのがあります。なんらかの現象のきっかけとなるおまじない的な使い方ですね。ある程度手前に距離を取ったほうが動かしやすいので、いろいろと試してみてください。


続いて、サトルティ的な使い方の紹介です。ピンキーブレイクを隠蔽するというか、ブレイクの印象を無くす使い方です。デック中程でピンキーブレイクしたときに、直後、あえてエンドリフルをしてブレイクの印象を無くすことができます。このとき、手前エンドもブレイクより上をリフル→観客側エンドをリフルと、両エンドをリフルすることでさらに効果が高まります。
最後に、手前も観客側も両方のエンドにいえることですが、特に意味もなく手癖的にリフルしたりします。デックを揃える動作の締めに「シュッ、シュッ」と両エンドをリフルする感じです。なんの意味もないですが、なんとなくいい感じの仕草に見えます。
コーナーリフル
続いてコーナー部のリフルです。主に観客側の2つのコーナーですが、右と左で使う指も弾く方向も変わります。
観客側右コーナーをリフルする
やり方
観客側右コーナーのリフルです。右手中指でボトムからトップに向かってリフルします。

デックが観客側に突き出るようなディーリングポジションで持って、右側に大きめに押しビベルします。

右手中指を観客側右コーナーのボトム側に当て、右手親指をトップ添えてそれを支点に中指をトップ方向に引いてリフルしていきます。
使いみち

主に「ピークコントロール」のときのやり方です。ピークコントロールについてはそのうちちゃんと解説しますが、フェイスが観客を向くようにデックを立てて右コーナーをリフルして、ストップをかけたところのカードを見て覚えてもらうカードの選択方法です。
ピークコントロールは実際にはシークレットムーブで、観客の選んだカードをただちに知るには使い勝手の良い簡単な技法なので、近いうちに解説しますね。今は、へーそんなのあるんだなと思っていただければ大丈夫です。
観客側左コーナーをリフルする
やり方
観客側左コーナーは左手の親指でトップからボトムに向かってリフルします。



ディーリングポジションから伸ばした人差し指をボトムに当てるか、曲げた人差し指をボトムに当てるかして、人差し指を支点に親指で観客側左コーナーをトップからボトムに向かってリフルしてください。
そこそこの腕力が必要なので、慣れないうちは人差し指を曲げたほうが力が加わりやすいかもしれません。
使いみち
使いみちの1つ目は、カードの選択に使えますね。リフルしてストップがかかった箇所のカードを観客のカードとします。ストップの箇所でデックを分けて、上パケットのボトムカードでもいいし、下パケットのトップカードでもいいですね。

2つ目は、1枚のカードをデックに戻すときですね。左コーナーをリフルしてデックの真ん中あたりで止めて、右手に持った1枚のカードをそこに差し込みます。ダイアゴナルパームなんかのときの差し込み方がそれです。
サイドリフル
最後はサイドのリフル方法です。2種類あります。
テーブル上のデックをリフルする
まずは、テーブル上に置いたデックのサイドをリフルするやり方です。
やり方

デックを横向きに置いて、手前サイドに親指、反対側のサイドに中指・薬指・小指、人差し指はトップに添えて、親指でボトムからトップに向けてリフルしてください。
使いみち



主な使いみちはテーブルリフルシャッフルのリフルなので、デックを2つのパケットに分けて、左右同時に練習してみてください(実際に、テーブルリフルシャッフルしちゃっていいと思います)。その際に、リフルする箇所を、内側のコーナー付近、真ん中、外側のコーナーといろいろ変えて練習するのが効果的です。



また、テーブルリフルシャッフル型のフォールスシャッフルに関わってくることですが、リフルのスピードコントロールを自在にできるようになるべきです。具体的にはどういうことがというと、左右で枚数の違うパケット(左が1/3で右が2/3とか)でテーブルリフルシャッフルをして、左右のリフルが同時に終わるようにする、とかです。今の例では、結果的にいえば左右のリフルのスピードを変えて帳尻を合わせているってことですよね。そういったコントロールができるようになっておけば後々役に立つでしょう。
左サイドをリフルする
最後の最後、手に持ったデックの左サイドのリフルです。
やり方

右手にエンドグリップで持って、左手を使って大きめのビベルを作って左サイドを傾斜させます。

ボトムに当てた左手中指と薬指を支点にして、左手親指で傾斜になった左サイドをトップからボトムに向けてリフルします。
使いみち
これもまたカードの選択に使える方法です。リフル中にストップをかけてもらって、そこのカードを観客のカードとします。
また、この動きは特定のカードを観客に選択させる場合にも使えます。「サイドリフルフォース」と呼んでいる簡単な部類のフォースですが、本編からは外れる話題なので、最後に「蛇足」で解説しましょう。
まとめ
リフルの解説は以上です。お疲れさまでした。
それ自体はなんてことのない技法ですが、関連技法を挙げたらキリがないほど様々な技法のクオリティに関わってくるものなので、ちゃんとできるのは当然のこととして、しっかり両手に馴染むよう練習してください。
リフルの習熟度がどれくらいかは、次(以下)のことをチェックすればいいでしょう。
リフルの習熟度チェックリスト
- 最初から最後まで1枚ずつ弾けること
- スピードのコントロールができること
- 速く
- ゆっくり
- 途中で速度を変える
- 目的の箇所で止められること
こんな感じですかね。今回はこれで終わります。
では、また。
sobogaの蛇足
サイドリフルフォースの解説
蛇足では、「サイドリフルフォース」を解説します。蛇足で何かを解説するのは初めてじゃないですかね。あれ、違うかな。忘れましたが。
では、やり方です。


本編で解説した、左サイドのリフルでカードを選択する形でのフォースで、フォースカードはボトムにセットされている状態から技法を行います。

左手でビベルを作ったらその流れで中指・薬指・小指を使ってボトムカードを右にズラします。ズラす幅はインデックス分くらい、上の写真くらいですね。


あまり大きくズラしてしまうと、今度は右側からフラッシュしてしまうので気をつけてください。

そして、ボトムカードをズラす際には、左手人差し指を中指の爪辺りに当てて、ボトムカードが移動していくところがフラッシュしないように人差し指をスクリーンにしてください。


ボトムのフォースカードをズラせたら、そのままリフルを始めて観客にストップをかけてもらいます。ストップがかかったら、その箇所に親指を差し込み、ボトム側はフォースカードが無い部分を掴んで下パケットを左に引き出します。


下パケットを半分ほど引き出したら、人差し指と親指の間で挟む持ち方で持ち直し、最後まで引き出します。下パケットはそのままディーリングポジションに持ちます。



これでフォースカードは上パケットのボトムに残りましたが、上パケットからは少し浮いていてズレた状態なので、左手を使ってそれを直し、パケットを立てて観客にフォースカードを見せたらフォース完了です。
技術的には簡単な部類のフォースになるので、フォースする場合とフォースしない場合で見た目が同じになるように練習して活用していただければと思います。
個人的にはヒンズーシャッフルフォースが「あまりにも・・・」な技法だと思っているので(マジックを学ぶ前から「いくら切っても一番下のカードは変わらないじゃん」って思ってた)、ヒンズーシャッフルフォースの代わりにサイドリフルフォースを使ったりしています。
サイドリフルフォースの解説はこんな感じです。
あらためて、では、また。
参考文献
おすすめカード
関連記事
Advertisement